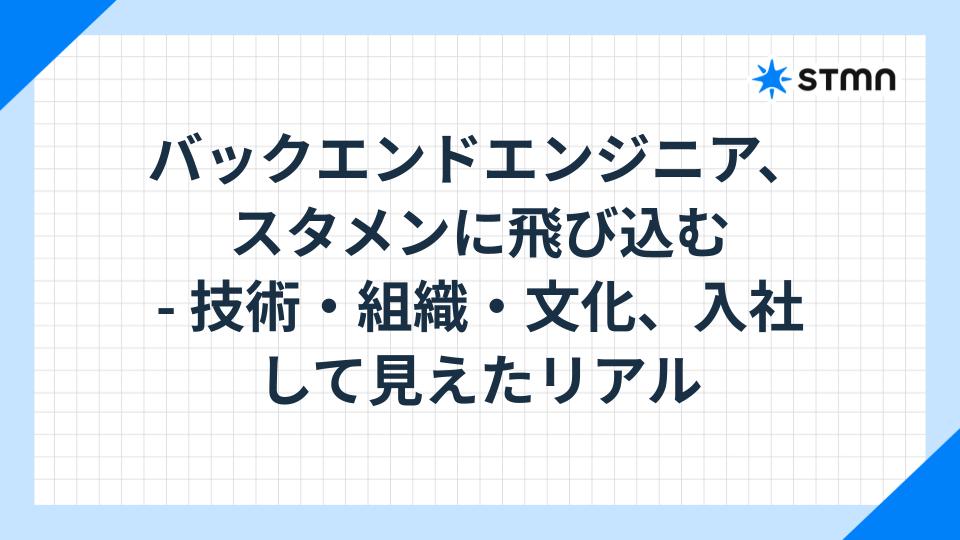
はじめに
こんにちは!株式会社スタメンにバックエンドエンジニアとして 2025年1月 に入社しましたもりしたです。
これまでは主にRubyを使ったバックエンド開発に携わってきました。現在は、SRE(Site Reliability Engineering)やDevEx(Developer Experience)の向上をミッションとするプラットフォーム部に所属しています。
この記事は、
- スタメンの採用サイトを見て、少しでも興味を持ってくださっている方
- カジュアル面談を受けてみようか迷っている方
- 実際に入社したメンバーの「生の声」を聞いてみたい方
に向けて書いています。
入社から約4ヶ月経過した今、肌で感じているスタメンのリアルな姿をお伝えすることで、皆さんの疑問や不安を少しでも解消できれば嬉しいです。
スタメンを選んだ理由 - 新たな技術領域への挑戦と、運用経験への意欲
私がスタメンを選んだ理由は、大きく分けて二つあります。
一つは、SRE(Site Reliability Engineering)やDevEx(Developer Experience)といった、これまで深く関わることがなかった新しい技術領域に挑戦できる環境への強い期待です。自身のスキルセットを広げ、より市場価値の高いエンジニアを目指したいと考えていました。
そしてもう一つは、プラットフォーム部でシステムの安定稼働を支えるための知識やスキルを習得したいという強い意欲があったからです。これまでの開発経験に加え、インシデント対応の調査や分析といった運用経験を積むことは、エンジニアとしての幅を広げる上で不可欠だと考えています。
カジュアル面談では、主にスタメンの事業内容や技術スタック、チームの雰囲気などについてお話を伺いました。その中で、プラットフォーム部がシステムの信頼性向上に重要な役割を担っていることを知り、開発だけでなく、運用という側面からもサービスを深く理解し、貢献できる環境に魅力を感じました。
スタメンの経営理念ページに書かれている Our Value(行動指針) の1つに 「Work Bravely(大胆に攻め、失敗や挑戦を讃える)」 があります。私はこの Value に背中を押され、未経験の領域にも積極的に踏み出すことを後押ししてくれる文化があると感じ、運用経験を通じて得られる知見は、今後の開発業務においても必ず活かせると確信し、入社を決意しました。
現在の業務内容 - 新しいことへの挑戦と学びの日々
プラットフォーム部の一員として、現在は主に以下の業務に携わっています。
- ライブラリのバージョンアップ対応: アプリケーションの安定性とセキュリティを常に高いレベルで維持するため、Dependabot を活用し、原則として平日毎日ライブラリのバージョンアップ対応を行っています。日々の小さな変更を積み重ねることで、常に最新の状態を保ち、セキュリティリスクを最小限に抑えています。バージョンアップの際には、影響範囲の調査や動作確認を丁寧に行い、システム全体の理解を深めています。
- プロジェクトメンバーとしてのバックエンド開発: プラットフォーム部のミッションであるSRE/DevEx向上に繋がる開発だけでなく、プロダクト開発のプロジェクトにもバックエンドエンジニアとして参加し、機能開発などを担当しています。最近では、TUNAGが提供するタスク機能に関わる開発に携わっています。
- オンコール担当: システムに問題が発生した際に迅速に対応できるよう、チームメンバーと交代でオンコール対応も行っています。スタメンでの経験はまだ浅く、原因特定に時間がかかることが多いですが、チームメンバーの協力を得ながら緊張感と責任感を持って取り組んでいます。
プラットフォーム部では、現在少数のメンバーで、SREやDevExに関わる幅広い業務を協力して進めています。ライブラリのバージョンアップ対応、機能開発のサポート、オンコール対応などを担当する中で、それぞれの得意なことや興味のある分野で助け合いながら、日々業務に取り組んでいます。少人数のチームだからこそ、お互いのスキルや知識を補完し合いながら、幅広い技術領域に触れることができています。
入社して分かったスタメンの特徴 - 期待を超えたリアル
実際に入社してみて、「なるほど、スタメンはこういう会社なのか!」と感じた特徴をいくつかご紹介します。
技術的な特徴 - 常に進化を求める姿勢
- Dependabotによる継続的なライブラリ更新: Dependabotを活用した自動更新の仕組みがしっかりと根付いており、常に最新の技術を取り入れ、セキュリティリスクを低減する意識の高さに驚きました。
- トランクベース開発: 頻繁なマージと迅速なフィードバックループにより、開発スピードと品質の両立を目指すトランクベース開発を採用していることで、チームの一体感と効率的な開発を実感しています。
- AI技術の積極的な活用推奨: 開発効率や生産性向上のため、GitHub Copilotなどを多くのエンジニアが利用しており、新しい技術へのアンテナの高さと、それを積極的に取り入れようとする文化を感じています。Devin の活用状況については、こちらのブログ記事をご覧ください。
組織的な特徴 - フラットな連携と成長支援
- 東京・名古屋の二本社制とフラットな連携: スタメンは東京と名古屋に本社を置く二本社制を採用しており、エンジニアは両オフィスに在籍しています。しかしながら、物理的な距離を感じさせないスムーズなコミュニケーションが取れており、拠点に関わらずチームとして一体感を持って働けています。
- 社員コミュニケーション促進の仕組み: 社員同士の交流を活発にするため、社内での懇親会や部署を超えての交流イベントなどを定期的に開催しています。
- 技術カンファレンスへの積極的な参加支援: 会社として、エンジニアの成長を支援するため、技術カンファレンスへの参加を積極的に推奨し、参加費用の補助などの支援制度を設けています。最近では、RubyKaigi 2025 に他部署を含めたバックエンドエンジニア全体で参加し、最新のRuby言語に関する動向や他社のエンジニアとの交流を通じて多くの刺激を受けました。カンファレンスで得た知識や刺激は、日々の業務における議論のきっかけとなるだけでなく、エンジニアとしての成長の糧となっています。
会社の雰囲気 - 挑戦を後押しするカルチャーとオープンな対話
- 賞賛を大切にする文化: 日々の業務における成果や貢献に対し、部署や役職に関わらず互いに賞賛を送り合う文化が根付いています。
- オープンなコミュニケーション: 部署や役職の垣根を越えて気軽にコミュニケーションが取れる雰囲気があり、会社全体の動きや目標を共有しやすい環境です。
- 東京オフィスの特徴: 私が所属する東京オフィスは、ビジネスサイドのメンバーが多く、オフィス全体が活気に満ち溢れています。様々な部署のメンバーが活発にコミュニケーションを取っており、エネルギッシュな雰囲気の中で業務に取り組むことができます。
さいごに
入社してまだ日は浅いですが、技術的な挑戦ができる環境、そして部署や拠点を越えて協力し合う組織文化の中で、日々多くのことを学び、刺激を受けています。
この記事を読んで、スタメンに少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。
スタメンでは、プロダクト開発に関わる全ての領域でプロダクト職種の採用をしています。
プラットフォーム部に興味を持っていただけましたら、Site Reliability Engineer (SRE)、ソフトウェアエンジニア(Developer Experience)からご応募ください。皆さんとお話できるのを楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。